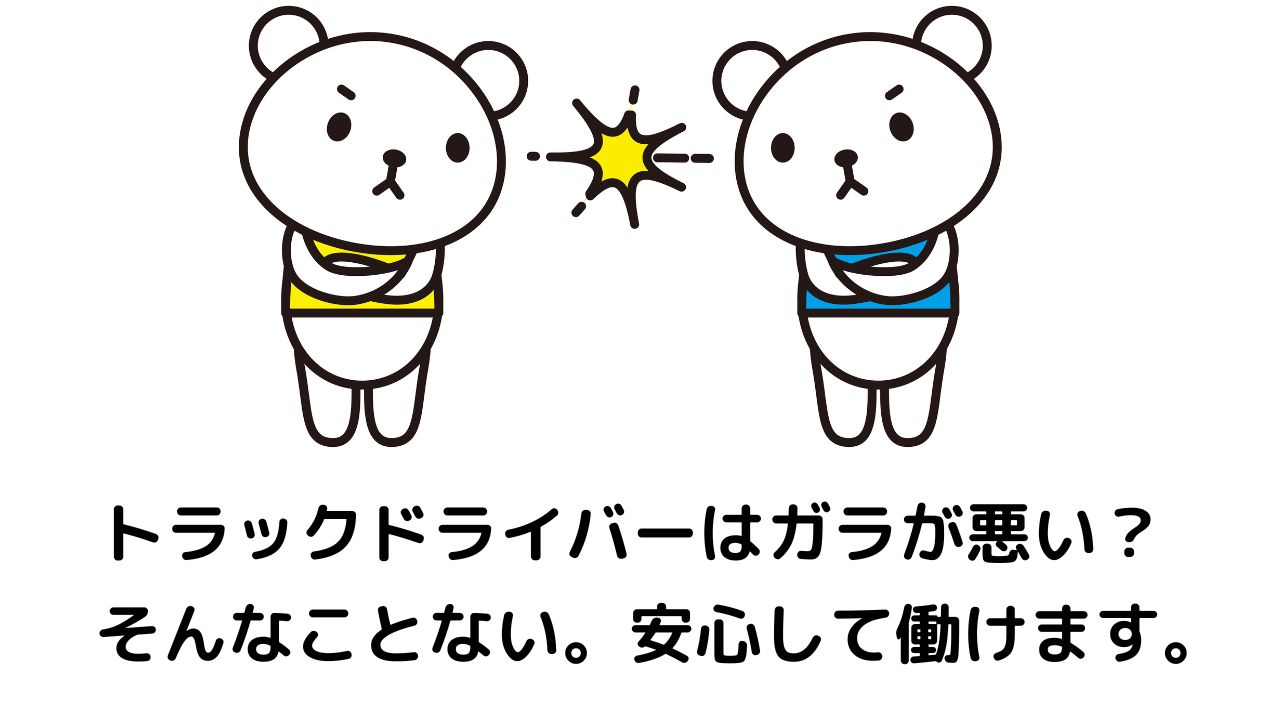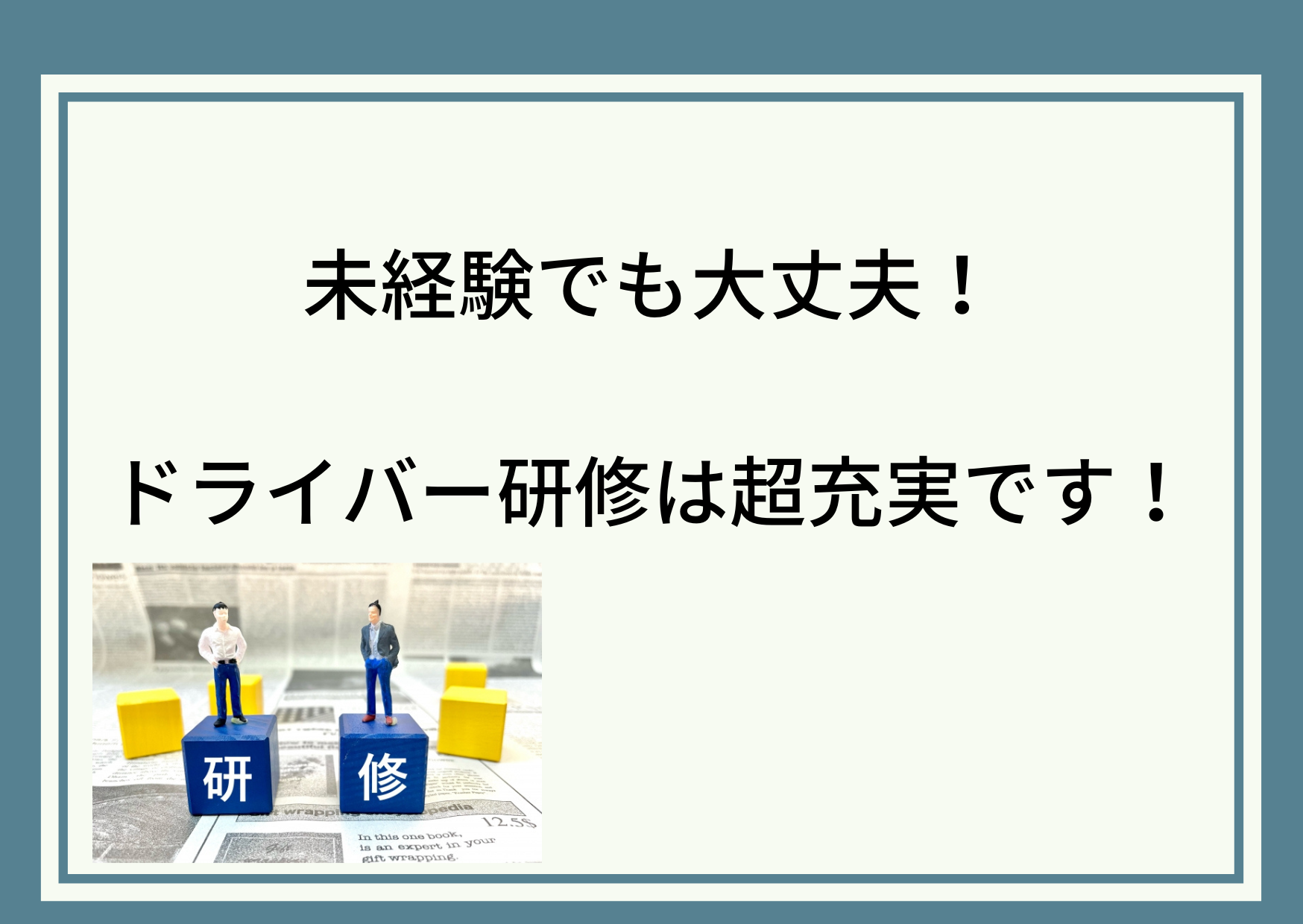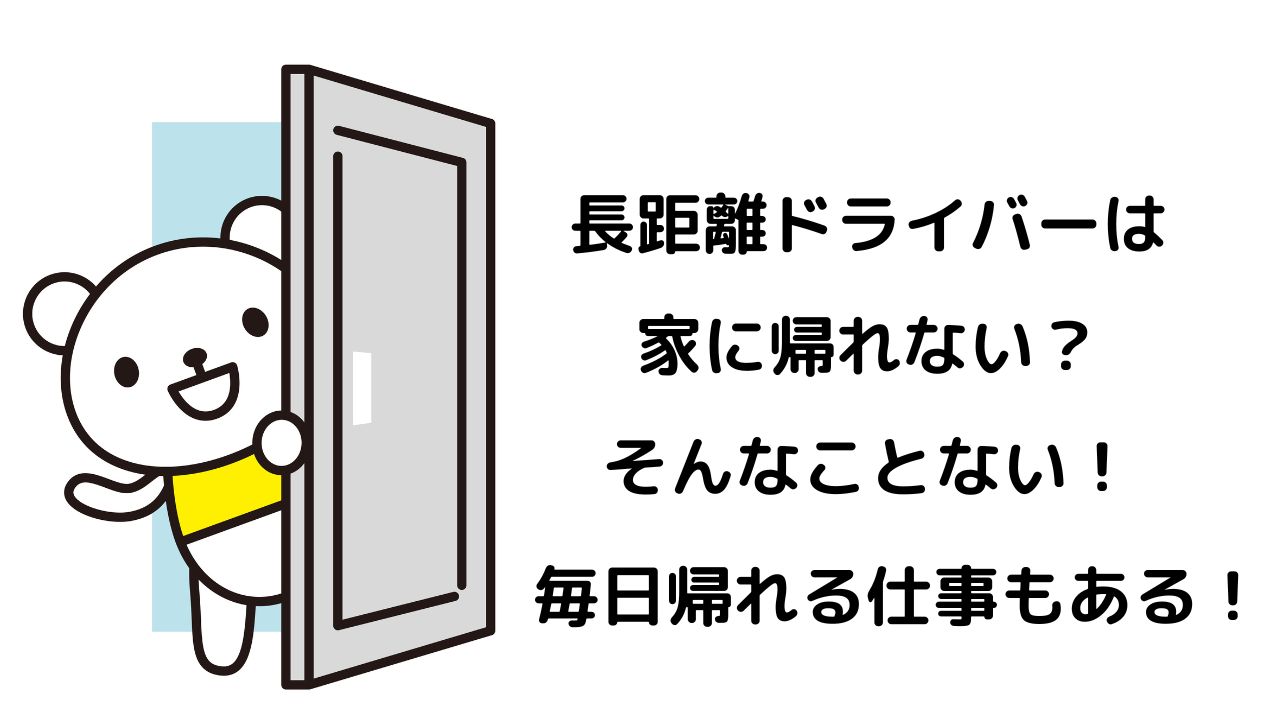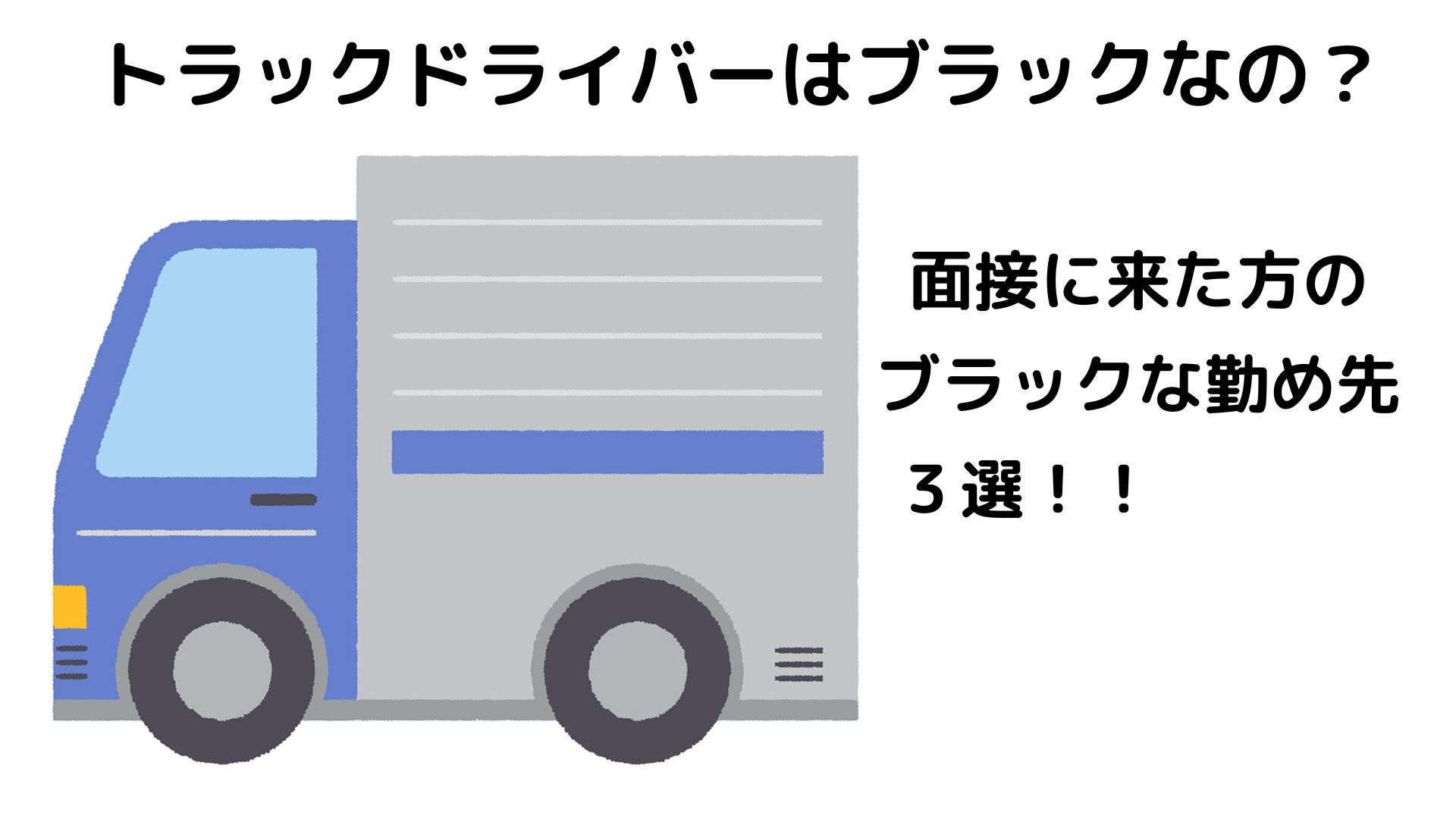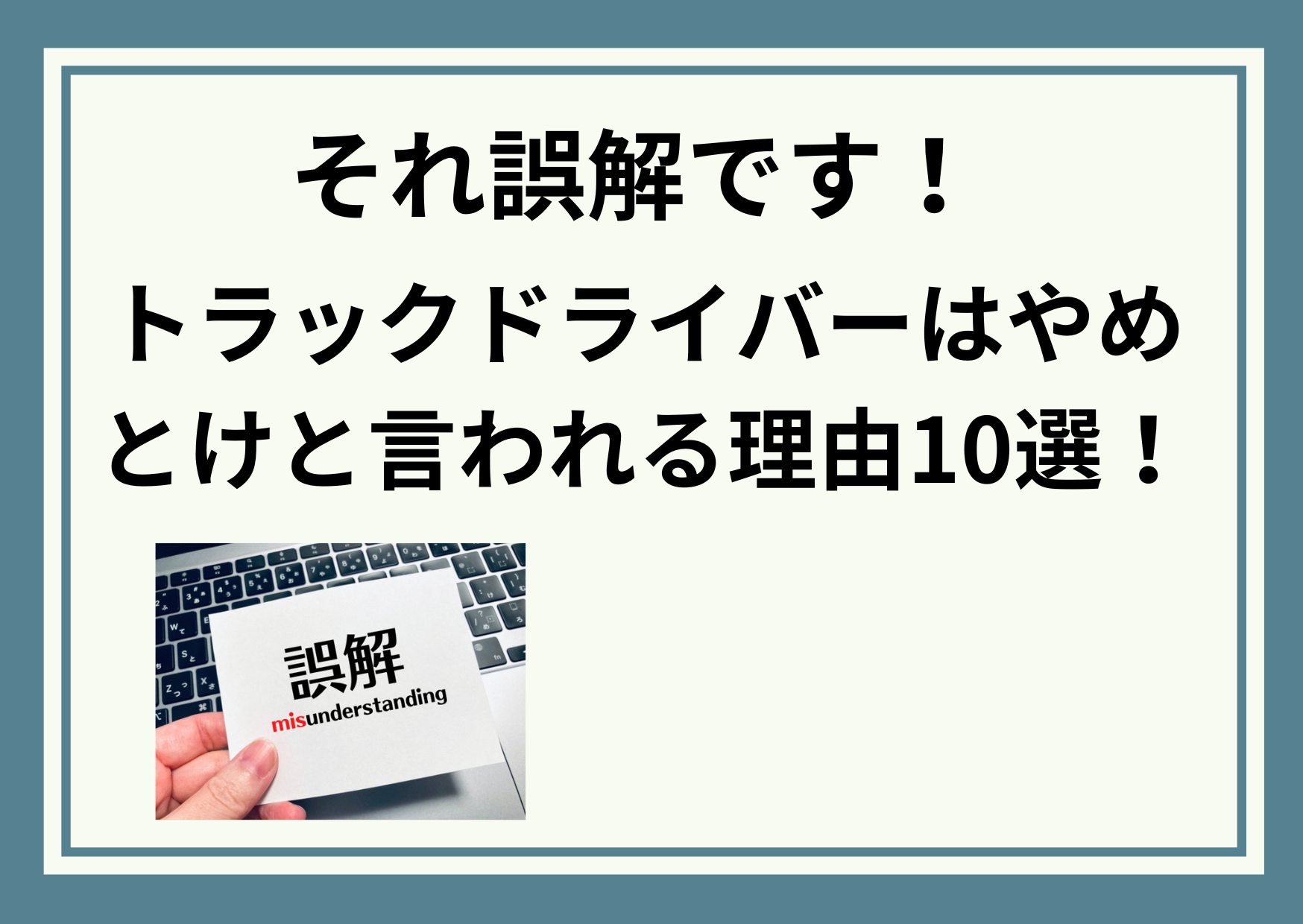【休める会社増加中!】トラック運転手でも休日は休めるし有給も取れます。ただし会社によります。
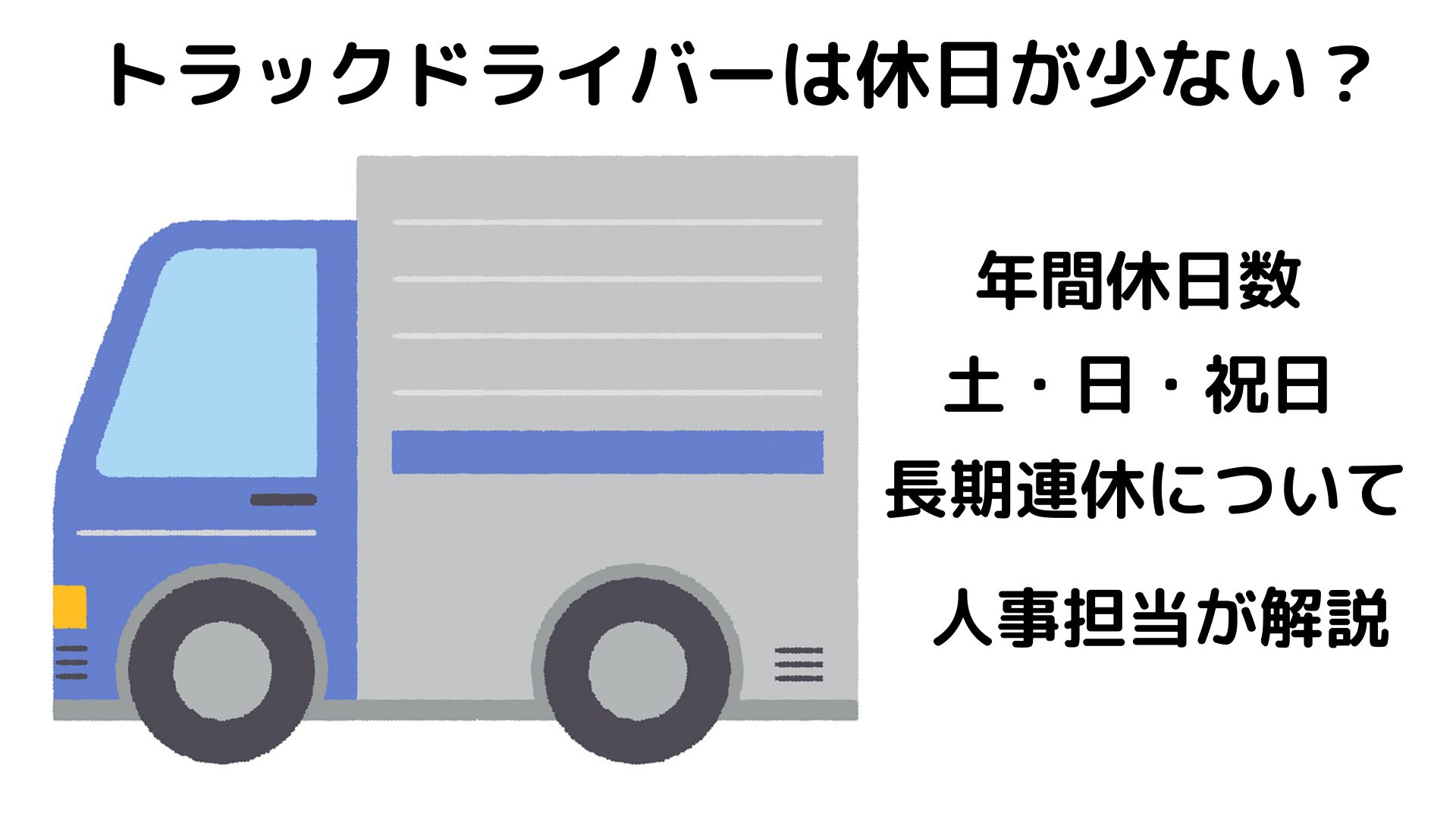

このサイトはあなたの「分からない」と一緒に成長しています。
分からないことがあれば下記フォームから何でも質問してください。
お答えできる範囲内で24時間以内に返信いたします。
- トラックドライバーは休みが少ないからブラック企業だ
- 土・日・祝日が休めないから家族サービスができない
- 家族に不幸があった日も休めないような気がする
- 運送会社はどこも休めないんじゃないの?
- 運動会なんかも参加できないんじゃないの?
- 1週間程度の連休が取れないからプライベートが充実しない
- 長距離ドライバーと集配ドライバーでは休みの取り方は違うの?
このような不安からトラックドライバーに転職することをためらっている方も多いのではないでしょうか。
確かにトラックドライバーの種類や勤める会社にによっては休みが少なかったり、連休が取りにくかったりもします。
しかし、休めるか休めないはどのような会社に入社するかで変わってきます。
・休めるかはどの会社・どの職種かによる
・トラックドライバーは年間100日以上休日の会社が多い
・宅配業は土・日・祝日の配達はローテーション
・路線業は土・日・祝日も休みやすい
・しっかり休みたいなら中堅~大手運送業に転職しよう

現在、従業員が3,000人程度の運送業で採用担当の仕事をしています。
詳しいプロフィールはこちらです。
トラックドライバーは休めないという悩みを解決する為にこの記事を書きました。参考になれば幸いです。
結論:休めるかはどの会社に入るかで決まる

休めるかはどの会社でどんな職種のドライバーになるかで決まります。
経験者で休みが少なく転職を考えている人も、これからトラックドライバーになろうと考えている人も必読の記事です。
私の勤める会社も掲載することが多い、お勧めの転職サイトを掲載しておきますので、さっそく転職を申し込んでみましょう。

トラックドライバーは他業種と比べて休めない仕事ではない

他の業種と比べた場合でも休日は少なくない
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によりますと、労働者1人当たりの平均年間休日数は116日となっています。
トラックドライバーのでも概ねこの数字に沿った求人が出されていることが多く、大手運送業では他の職種に比べて休日が少ないとはいえません。
逆に、休日が年間100日を下回る場合は、給料が他の会社と比べて著しく高い場合などを覗いて避けた方が良いでしょう。
特に、同じくブラック企業といわれる飲食業と比べるとかなり恵まれていると思います。(実際に飲食業の方が面接に来るとおどろかれます。)
私の勤める会社では、年間休日112日に加えて、任意に使える自己啓発休暇というものが2日ありますので、実質114日の休暇となっています。
休日は会社の規模による差が大きい
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によりますと、企業規模の平均休日日数は下記の通りとなっています。
- 1000人以上の企業・・・・120.1日
- 100人~999人の企業・・・115.8日
- 30人~99人の企業・・・・109.6日
運送業においても、概ねこのイメージで間違いないありません。
大手運送業にはトラックドライバー以外にも事務職、営業職等の内勤を多く抱えています。
トラックドライバーは働いだだけ多く給料がもらえる職能給性がとられていることが多いため、できるだけ多くの日数を働きたがる方が多いのですが、内勤の方は固定給ではたらいているためできるだけ少ない日数で働きたがります。
内勤者を採用するためには他の業種との取り合いになるため、他の業種と同じように休日日数を増やす必要があります。
そして同じ会社で休日日数を違えることができないため、必然的にトラックドライバーの休日も増えることになるのです。
したがって、できるだけ人数が多く大きな会社に転職した方が休日を確保しやすくなります。
年間休日が多くても実際に休めるのかは別問題
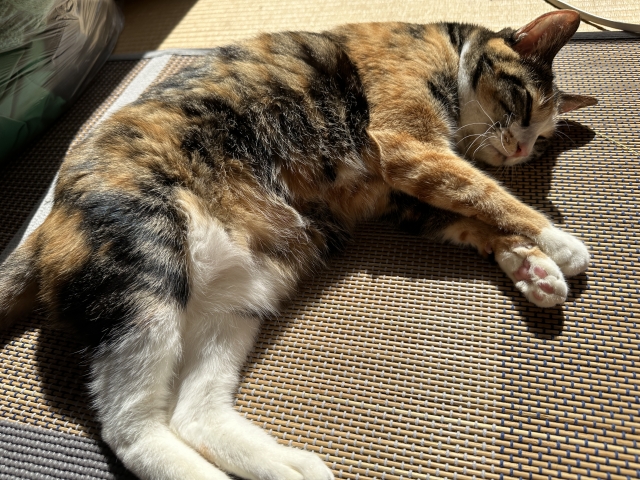
休めないドライバーの割合について
年間休日が多く設定されていても、実際に休めなければ絵にかいた餅です。
令和3年の国土交通省の調査では、トラック運転手の休日について、次のような報告が出されています。
【7日間のうち休日がなかったドライバーの割合】
| 普通トラック | 3.2% |
| 準中型トラック | 6.6% |
| 中型トラック | 6.8% |
| 大型トラック | 11.9% |
| トレーラー | 9.5% |
| 全体平均 | 9.4% |
この結果をみると、全トラック運転手の約1割、つまり10人に一人くらいが、1週間に1日も休めていないことになります。
休める休めないは会社による
ここで間違わないでほしいのは、トラックドライバーの全体の1割が休めないのではなく、9割以上を占めるしっかり休める会社と、1割程度の休めない会社が存在しているということです。
大規模で資金力のある会社は、ある程度高い賃金を支払うことができるので、ドライバーの確保が比較的容易であり、人員に余裕を持っています。
完全週休二日制を導入できているのも、大企業が中心になっています。
これに対して、一部の中小運送業は高い賃金を提示できず、ドライバーの確保が困難になり、その結果、休日出勤が発生することになります。
それでは、トラックの車種別ではどうでしょうか?説明していきます。
大型長距離ドライバーは急には休みづらい

急に休みを申請されても代わりの人員がいない
大型長距離ドライバーの仕事は、出発した営業所から他府県へ長距離輸送を行います。
集配ドライバーと違い、急な欠員が出たからと言って近隣のコースを走っているドライバーにたすけてもらうことはできません。
例えば、大阪~東京方面へ走っているトラックドライバーに欠員が出た場合に、大阪~新潟を走っているドライバーに寄り道してもらうことはできないということです。
そのため、大型長距離ドライバーのシフト管理は運行管理者により細かく管理されていることが多く、急な休みはかなり嫌がられることになります。
最近導入が増えている「ジョイント輸送」については、相手方のドライバーの都合もあるため、さらに休みにくくなります。
「ジョイント輸送」についてはこちらの記事も参考にしてください。
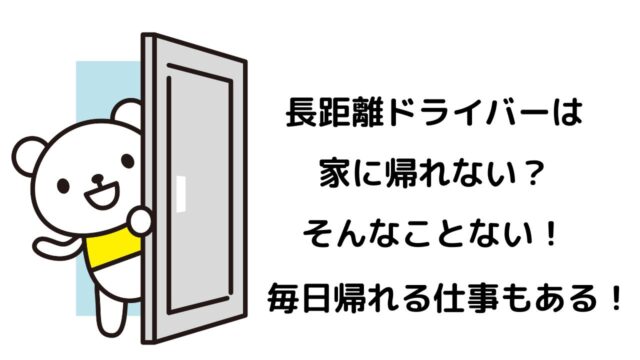
休日はしっかりとシフト管理されている
急な休みがとりづらいからと言って、休みが取れないわけではありません。
トラックドライバーは休憩時間や、1運行時間の上限が定められており運行回数などがしっかり管理されています。
急な休みは取りにくくても、休めないということはありません。
トラックドライバーでも土・日・祝を休める

トラックドライバーも土・日・祝日は休日にできます。
ただし、これは会社の業態によって大きく変わってきます。路線便は休みやすく宅配便は休みにくいです。
BtoCの宅配業は土・日・祝日は休みにくい
BtoCとは、企業から預かった荷物を個人宅に配達する仕事です。BtoCので一番に思い浮かぶのが、宅配業です。私たちがネット通販でお買い物した場合お世話になっていますね。
ほとんどの運送業は、指定された日の指定された時間に届ける必要があります。
その中でも宅配業は、個人宅に配達しているため、在宅している土・日・祝日を指定されることが多く、必然的に出勤が多くなります。
もちろん、ドライバーの数を確保できている会社であれば、ローテーションを組みながら休日を確保している会社もあります。
しかし、新人や独身者にしわ寄せがきているケースも多々見受けられます。
土日祝日に必ず休みたい方は、宅配業は避けた方がよいでしょう。
BtoBの運送業なら土・日・祝日に休みやすい
BtoBとは、ビジネスからビジネス。つまり、企業から企業へ荷物を届けている仕事です。
この業種の運送業は、集荷先・配達先がともに会社や商店、企業となります。
ほとんどの企業は、日曜日・祝日が休日となっているため、それらの企業と取引している運送会社も休日となります。
最近では週休二日制を導入し、土曜日も休日としている企業も増えており、。当然それらの企業と取引している運送会社も休日となります。
もちろんすべての企業が土曜日を休日としているわけではない(例:荷物の出荷は無いが、体辰の荷受けはしている場合、この場合は配達要員として出勤する必要がある)ので、すべての土曜日が休日となるわけではありませんが、比較的休日を取りやすい(隔週出勤・半日業務等)と言えるでしょう。
ただし、コンビニやスーパーマーケット等、365日営業している企業が取引先の場合はこ休みがとりにくいので注意が必要です。
以上のように、土曜日を完全に休日とすることは難しいのですが、日曜・祝日を確実に休日にしたいのであれば、BtoBの運送会社(具体的には路線会社等)から選ぶとよいでしょう。
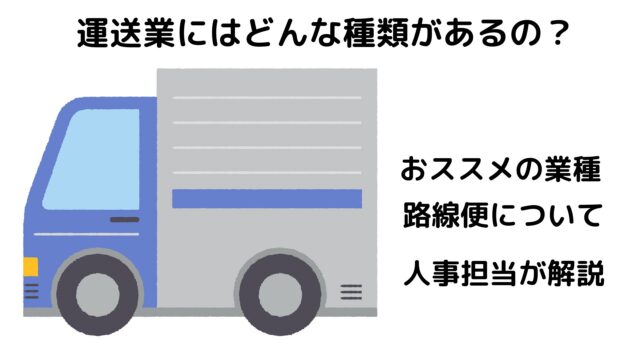
トラックドライバーは長期休暇が取れないのか?

土・日・祝日と並んで、トラック運転手が取得できないと思われているのがゴールデンウィーク等の長期連休です。
結論から言うと、小規模宅配会社では取得が難しく、大規模路線会社では取得しやすくなっています。
BtoCの宅配業は難しい
先ほどの項目と同様に、宅配業で長期休暇を取ることは難しいと言えます。
一般的に、長期休暇を取りやすいのは、GW・お盆・年末年始といったところでしょうか。
しかし、みんなが休日になると忙しくなるのが宅配業です。
GW・お盆で親族が集まった場合に、「クール便で産直品を取り寄せてみんなで食べよう」そう思ったときに配達してくれるのが、宅配業です。
「今年のお正月はおせちを取り寄せて豪華なお正月にしよう」そう思ったときに配達してくれるのが、宅配業です。
みなさんの長期休暇の楽しみを支えてくれているのが、宅配業です。
もちろん、大手宅配業ではローテーションを組んだりと、努力をしているのですが、長期休暇を取るのはそれでも難しいと言えます。
特に独身者や、新人にしわ寄せがくる傾向があるため注意が必要です。
BtoBの運送業(路線業)なら比較的容易
こちらも土・日・祝日と同じように長期休暇を取りやすい傾向にあります。
理由も同じで、GW・お盆・年末年始は取引企業も休日となっていることが多いからです。
取引先がコンビニ・スーパーマーケットの場合に注意が必要なのも同じです。
結論:BtoBではなくBtoCの会社を選びましょう
このように、長期連休を取りたいのであれば、企業との取引をしているBtoCの会社を選びましょう。
休日だけでなく有給休暇の取りやすさも重要
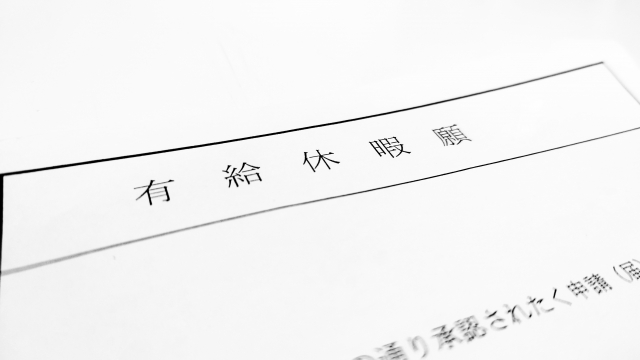
ある程度休日が確保できていたとしても、自分の休みたい日を休日にしたくはありませんか?それができるのが、有給休暇です。
わかりやすく言えば、休日だけれども給料がもらえる日のことを有給休暇と言います。
そんな素敵な有給休暇ですが、トラック運転手でも取得することができるのでしょうか?
結論としては、トラック運転手も労働者である以上、有給休暇は発生します。しかし、使用しやすいかは会社の環境によります。
そもそも有給休暇とは?
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。
簡単に言えば、取得しても賃金が減額されない休暇のことを言います。
有給で賃金が減額されないとは?
賃金が減額されないとは、そのままの意味で出勤した場合と同じ給料が保証されるという意味です。
しかし注意が必要なのは、トラック運転手は基本給と職能給が分けて計算されている場合が多く、運送会社の中には、基本給は補填するが職能給は補填しないといった会社も見受けられます。
私の勤める会社では、職能給もその月の平均を日数で割った金額を支給していますが、面接時に確認しておいた方が良いでしょう
有給はいつから何日もらえるの?
この疑問については、下の表をご覧ください。
| 入社日からの勤続期間 | 付与される有給日数 |
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月 | 20日 |
このように、入社後半年から発生する有給休暇は、発生後1年ごとに増えていき、6年6か月経過後は、1年ごとに20日発生することになります。
有給休暇をストックできるのは2年間だけ
このように発生する有給休暇ですが、永遠にストックし続けられるものではなく、最大でも2年分しかストックしておくことができません。
6年6か月以上勤めている方の場毎年20日の有給が発生するのですが、ストックできるのは最大で40日間です。
例えば、2023年に40日の有給残がある方の内訳は、2023年発生分の20日と2022年発生分の20日となります。
そして、2024分の有給が発生する時期になると、2022年分の20日間は消失してしまいます。
2024年→20日発生
2023年→20日(持ち越せる)
2022年→20日(消滅する)
そして、この消滅する有給休暇は復活することはなく、原則として買い取りもしてくれません。
まれに好意で買い取り(退職時に未使用分がある場合など)してくれる会社もあるようですが、本当に稀なので期待しない方が良いでしょう。
つまり、有給休暇の未使用は救済制度がなく、泣き寝入りすることになります。
したがって、有給休暇を使用できる会社に就職することに越したことはありません。
大会社のほうが有給を取得しやすい
休日と同じで、有給休暇も大企業のほうが取得が容易となっています。
理由も休日と同じで、大企業のほうが働いている運転手の数が多く、融通が利くからです。
5人しかいない運転手の1人が休むのと、50人いる運転手のうち1人が休むのとでは残りの運転手にかかる負担がずいぶん違うということはわかっていただけると思います。
また、大企業では新卒採用にも力を入れており、就職説明会では有給取得率も公表されています。
有給取得率が低ければ優秀な学生から見向きもされなくなるため、大企業では有給取得を吸い推進している会社が増えています。
では中小企業は従業員に有給を取得させないままでよいのでしょうか。そんなわけはなく、有給消化は国により法律で定められています。
会社は最低でも年5日の有給を使用させる義務がある
年10日以上有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者は年5日の有給を取得させる必要があります。
これに反すると違反者1人当たり30万円の罰金が使用者に課されることになります。(労働基準法39条7項)
有給を取らせない悪徳経営者がはびこっていたためにできた法律です。もしあなたが、会社に有給申請したとして却下されていた場合は、この条文を根拠に戦うことができます。
ただ、経営者からしても問題なのは有給を取りたがらないドライバーの存在です。
有給を取りたがらないドライバーもいる
有給なんて取れれば全部取りたいを思うのが労働者ですが、ドライバーの中には有給を取りたがらない人もいます。
トラック運転手の多くは、その給与形態が完全な固定給ではなく、固定給+歩合給という形で支給されていることがほとんどです。
有給を取得した場合、固定給のみならず歩合給の部分まで支給されるのであれば問題ないのですが、会社によっては固定給の部分のみが支給される場合もあります。
このような場合では、有給を取ることにより歩合給を丸々失うことになるので、有給を取得したがらないということです。
有給取得時に給料のどこまでが補填されるかは、転職時にしっかりと確認しましょう。
このように、有給を取得しないドライバーばかりだと罰金を払わされることになりますが、経営者側から有給をあてがう制度があります。
これを有給の時季指定をいいます。
会社は有給の時季指定ができる
有給を取らないドライバーへの対抗手段として、会社には時季指定権が与えられています。
時季指定権とは、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、事業主が5日分の日にちを指定して年休を取得させる方法です。
就業規則に定める必要があるなどの要件はありますが、これにより会社は有給を取得させることができ、違反金の支払いを回避することができます。
大会社のほうが有給を取得しやすい

大会社は人員に余裕があるから有給を取得しやすい
休日の取得しやすさと同様に、大会社のほうが有給の取得はしやすくなっています。
理由は人員が豊富なので、欠員が出ても仕事を回すことができるからです。
100人のドライバーがいて1人が休むのと、10人しかドライバーがいないのに1人休むのとでは、残りの人たちにかかってくる負担が大違いなのはわかっていただけると思います。
大会社は有給取得率を気にかけている
新卒社員に対して求人を出す際に、モデル年収や年間休日数、平均継続年数と並んで、有給休暇取得率を求められることが増えています。
有給取得率が低ければ、新卒社員が入社してくれないというわけです。
トラックドライバーは即戦力として中途採用でもいいかもしれませんが、内勤の事務スタッフや営業職員などは、やはり新卒で採用してしっかりと教育したいものです。
事務方もトラックドライバーも同じ企業に属する社員であるために、トラックドライバーに対しても有給消化を促している会社が増えています。
この記事の結論:休日・有給を取りたいなら、転職を考えよう
今の休み方に不満がある方は、転職を検討しましょう。
とはいえ、今の仕事を捨てて、新しい会社に就職すること・未経験から仕事を始めることは勇気がいることです。
そんな方にこの言葉を送ります。

「転職にはリスクがありますが、転職活動にはリスクがありません」人生を変えるためにも、積極的に転職活動をして行きましょう。